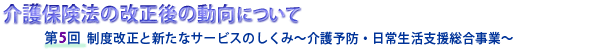3 地域ケア会議の多様な活用
1 個別のケース検討会から、地域の課題のニーズ・課題の把握と総合的な対応へ
地域の社会資源をどのように把握、創出するのか等について、個別の実態調査等を行って把握するのが正当であるが、多くの事例検討を行う場である地域ケア会議でそれを実現する流れが、24年10月26日の厚生労働省主催の市町村職員を対象とするセミナーで示された(図4のとおり)
図4 個別課題の解決から始める意義(参考例)
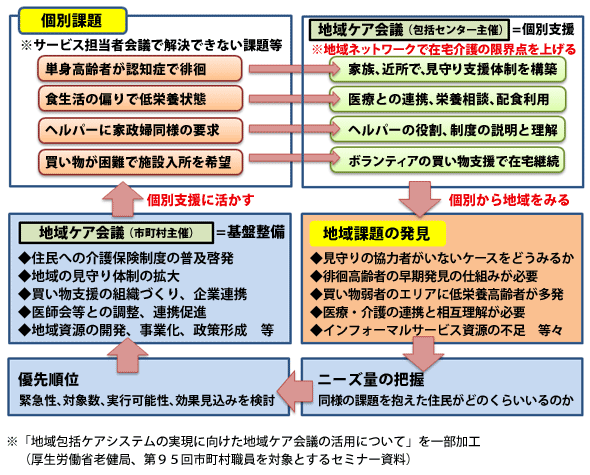
この参考例では、上記の図のとおり、個別のケース検討→地域のニーズの把握→社会資源の把握→社会資源の開発→さらにネットワークの構築へと向かい、その成果をもって地域の困難ケースへの対応というように、地域ケア会議の機能(図5)をめいっぱい活用している。
図5 地域包括ケア会議の主な機能
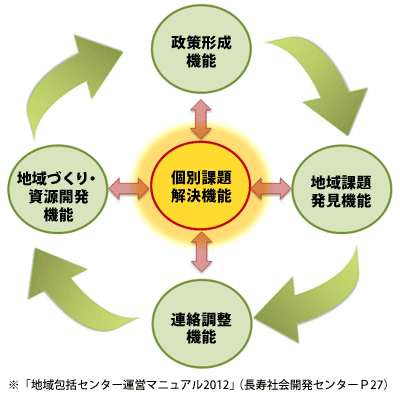
2 おわりに
介護予防・日常生活支援総合事業をみているうちに、地域包括ケアに、そしてケアプランの個別事例を支援する「地域ケア会議」に行き着きました。また、この総合事業が単独であるのではなく、地域包括ケアシステムの構成要素としても、地域ケア会議との関係においても、相互に関連しあっているようです。
ただし、地域包括ケアにしても、地域ケア会議にしても、最初に述べた背景を克服するための手法・手段として提起されているので、さらにより効果的な方法がすでに構築しているとするならば、あえてやり方を変えるメリットはないと思われます。逆に対応ができていないとすれば、積極的に対応する必要があります。このように見てくると、24年度改正は、関係者の意識の転換も視野に入れた、大きな改革といえます。
(参考)
- 「介護予防・日常生活支援総合事業の基本的事項について」(老振発0930第1号平成23年9月30日)各都道府県担当課・各市町村介護保険担当課・各介護保険関係団体あて厚生労働省老健局振興課長通知
- 平成23年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「介護予防・日常生活支援総合事業の手引き」(平成24年3月) みずほ情報総研株式会社
- 「地域支援事業の実施について」の一部改正について(老発0406号第2号平成24年4月6日)各都道府県知事あて厚生労働省老健局長通知