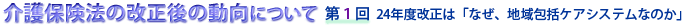
1 はじめに
24年度介護保険制度が改正されて2ヶ月半が経過しようとしています。今回の改正の目玉である「地域包括ケアシステム」がなぜ必要なのか、
なぜ医療連携が必要なのかについて、その背景等から、その必要性の理由等について考えます。また、その理由がある程度分かれば、地域包括ケアシステムという仕組みで求められているサービスやサービスを支える職員、そしてケアマネジャーの役割も見えてくると思われます。
まず、現在進行中の「社会保障・税一体改革」の中での社会保障制度の将来の方向性について介護医療の分野で見てみます。
財政悪化や高齢化が進展する中で、社会保障制度を今後ともに機能させるためには、財政需要の増加を抑え、制度の改革が不可欠との認識があります。
その将来像を、資料から見ると、次のようになります。
表1 将来人口推計
| |
平成23年度 |
平成37年度 |
23年度 |
37年度 |
| 総人口 |
127,753 |
120,659 |
1.0 |
0.944 |
| 高齢者人口 |
29,764 |
36,574 |
1.0 |
1.229 |
|
65ー74歳人口 |
15,044 |
14,788 |
1.0 |
0.983 |
| 75歳以上人口 |
14,720 |
21,786 |
1.0 |
1.480 |
*出典 国立社会保障・人口問題研究所
今から13年後、総人口は減少しますが、高齢者人口は約700万人増加します。しかし、増加するのは75歳以上の「後期高齢者」といわれている人口で、前期高齢者の人口は減少に転じます。
つまり、医療・介護のハイリスク層の人口が約700万人増加することになります。
その備えとして、制度改革ではどのような方向をめざすのでしょうか。
表2では、37年度には、800万人近い人が介護保険に該当し、650万人近い人がサービスを利用しています。これは現在と比べて、利用者数で1.5倍です。
高齢者の5人に1人強が認定を受けていて、高齢者の6人弱に1人が介護保険サービスを利用している計算になります。
表2 将来の認定者数見込みとサービス利用者数見込み
| |
|
平成37年度 |
|
| |
平成23年度 |
現状投影A |
改革B |
B/A |
| 要介護認定者数 |
5,222 |
7,988 |
7,914 |
0.99 |
| 高齢者比率 |
0.175 |
0.218 |
0.216 |
|
| 利用者数 |
4,260 |
6,470 |
6,410 |
0.99 |
| 高齢者比率 |
0.143 |
0.177 |
0.175 |
|
今より利用者数が1.5倍になるということは、それだけ財政負担が大きくなり、現状の考え方を踏襲すれば、介護保険料も1.5倍になりかねません。
生産年齢人口が減少する中で、果たしてそれに耐えられるのでしょうか。では、社会保障改革では、そこをどう考えたのでしょうか。

