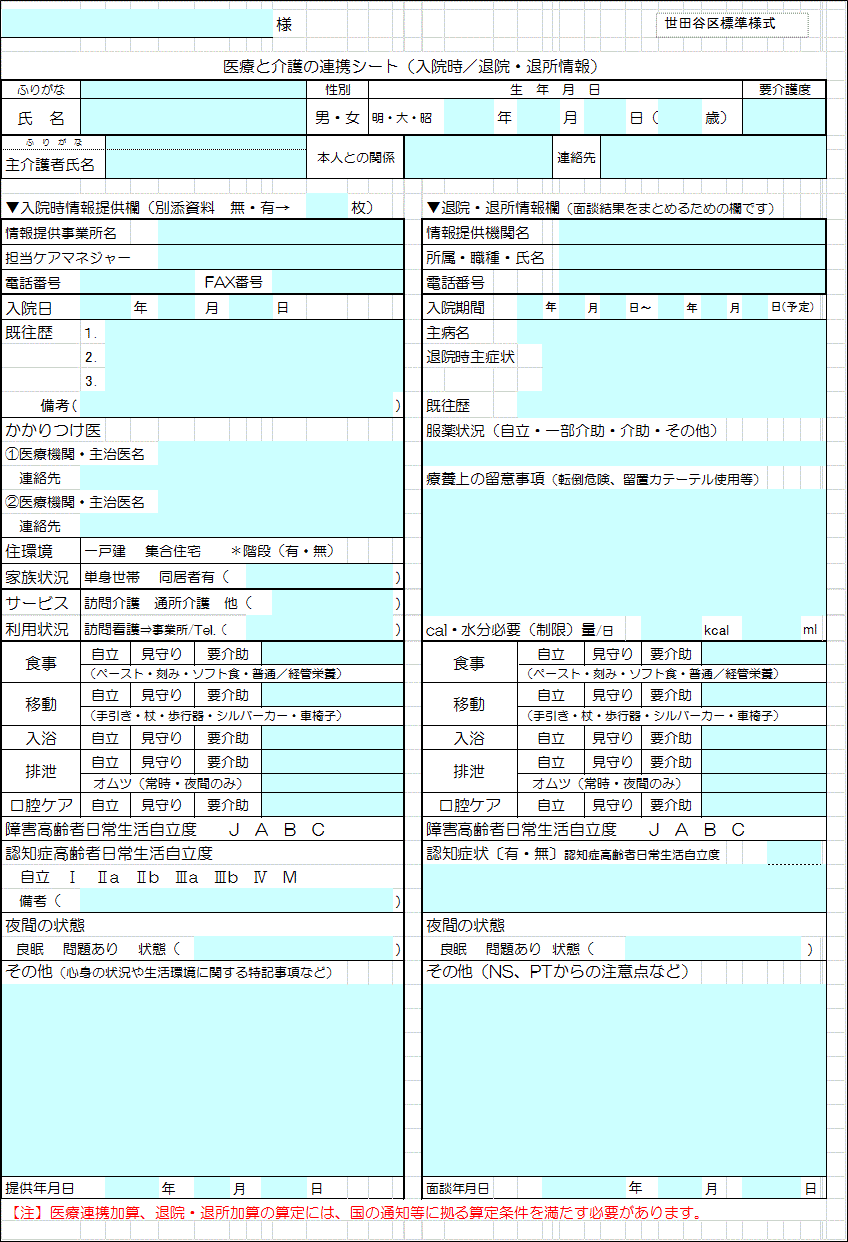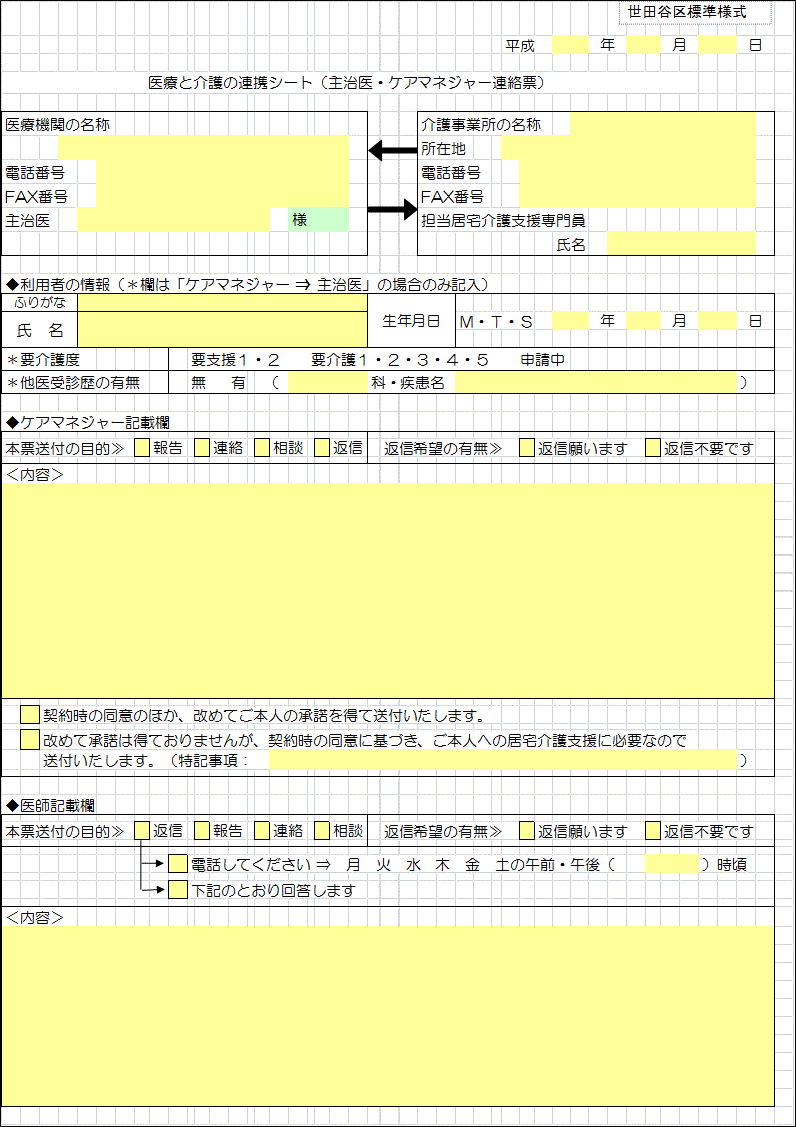3 期待される医療・介護の連携のしくみづくり
先に述べたことを満たすための医療・介護等の連携はどのように行われるのか。実際は、様々な地域には、様々な方法があると思われる。
しかし、いろいろな試みが行われているものの、なかなか連携の仕組みが実際に動いていないところが多いと思われる。医療介護連携が実現した上での、在宅での生活のための、要介護者のQOLの改善につながるケアプランの作成である。医療と介護の連携の仕組み作りとして、東京都世田谷区は以前より連携の様式等を作成していて、随時改定を行っている。ホームページで公表されているので、関心がある人は参照されたい。
1 世田谷区の方法等
医療連携の具体化が難しい中で、以前より連携の様式等を作成し、実施している世田谷区の特徴は何だろうか。 大きく三点あると思われる。
- 世田谷区が保険者としての調整機能を積極的に果たしていること
- 医師会や介護保険事業者等が医療と介護の連携に協力し合っていること
- 連携の様式が、見直され改定されていること
特に3については、実際に使用する中での改善を図っていると言うことだろう(様式は別添のとおり)。
実施できていない自治体においては、医療側の立場では、日本医師会も平成24年3月「地域を支える医療と介護の連携を目指して」-介護保険委員会答申-をまとめ、必要性・重要性を述べている。厚生労働省は平成24年度の介護保険法の改正で、その構築の必要性について強調している。ゆえに、後は、地域に医療と介護の連携ネットワークをつくることだけである。これは優先度の高い保険者の仕事であるが、その取り組みには相当の濃淡がでている。
2 ケアプランに反映させるきっかけとしての「地域ケア会議」
それらの医療・介護連携の仕組みの有無にかかわらず、医療との連携や社会資源を活用したケアプランを作成する必要がある。また、24年度からの促進が言われている「自立支援型ケアマネジメント」については、その実体化や普及が課題となっている。
そのような中で、地域包括ケアシステムの構築のためのケアプランをいかに作るかについて支援する場として「地域ケア会議」が提案されている。
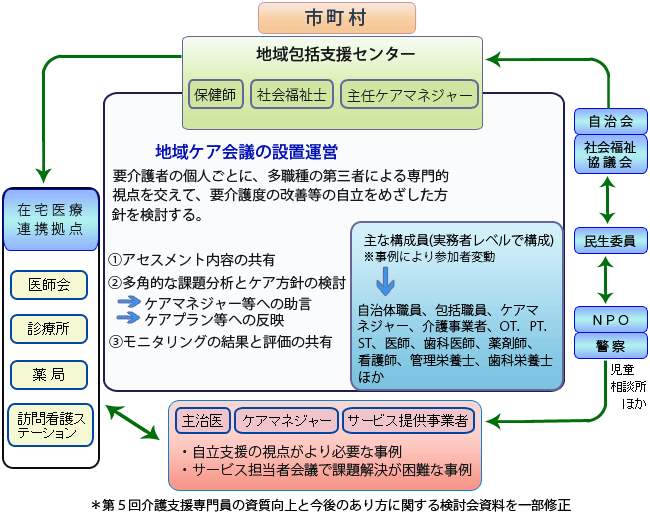
地域ケア会議は、例えてみれば、地域包括支援センターが行う「サービス担当者会議」のようなものである。地域包括の主任介護支援専門員等が、居宅介護支援事業所からあがってきた個別のケースについて、課題を把握して、必要なサービスをコーディネートし、ケアマネジャーが具体的なケアプランを作成するための、手助けをする場である。それ故に、そこには関係者が集まり(集められ)、多様な資源を活用したケアプランの案を作成することになる。
そこで作成するケアプランの案は、地域包括ケアシステムの実現に向けたケアプランということになる。