23年度モデル事業その他の概要
1 介護保険事業(支援)計画の基本的な考え方(地域包括ケアの推進)
 計画策定の際の地域ニーズの的確な把握について
計画策定の際の地域ニーズの的確な把握について
第5期介護保険事業(支援)計画の作成に当たっては、高齢者が要介護になっても可能な限り住み慣れた地域において継続して生活ができるよう、1.介護、2.予防、3.医療、4.生活支援、5.住まいの5つのサービスを一体化して提供していく「地域包括ケア」の考え方に基づき、取り組むことが重要。
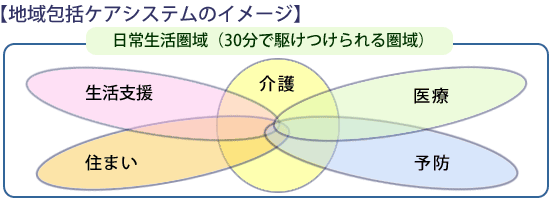
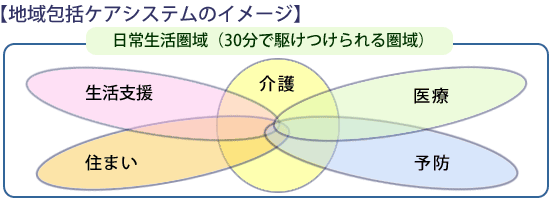
- 医療との連携強化
- 介護サービスの充実強化
- 予防の推進
- 見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護等
- 高齢期になっても住み続けることができる高齢者住まいの整備(国土交通省との連携)
○地域包括ケアの実現を目指すため、第5期計画(平成24~26年度)では次の取組みを推進。
|
||
※24年度改正の目玉は「地域包括ケアシステム」の実現です。これは第1回でも述べたように、社会保障の定義の転換「参加型社会保障(Positive Welfare)」について、当面、高齢福祉の分野で具体化を図ろうとするものと思われます。
コールがあれば、30分以内に駆けつけられるエリアを範囲として「日常生活圏域」を設定し、地域包括支援センター(ブランチを含む。)を整備し、在宅サービスの充実を図ることで、特別養護老人ホーム等の介護施設に入所しないで、地域で暮らし続ける仕組みを作ろうとする試みです。
その実現に向けた第5期介護保険事業計画の策定であり、その計画を実現するための、各種サービスの創設・整備となっています。
第5期介護保険事業計画の作成に当たっては、各日常生活圏域ごとの詳細なニーズ把握が求められるところです。また、関連して、そのニーズに対してサービスを提供する事業者について、地域密着型に関しては、従前の自由参入から公募制へと切り替えることで参入制限を図れる仕組みとなっています。併せて、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの普及を図ることで、これまで要件を満たせば自由に参入が可能であった訪問介護等の指定について、事前の区市町村との協議を必要とするように、考え方の転換を図っています。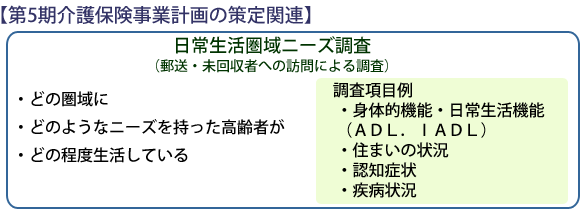
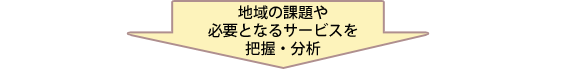
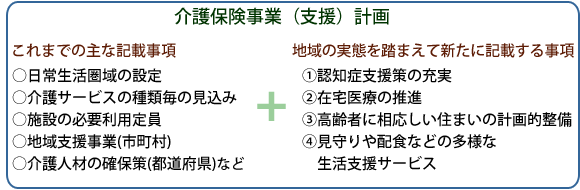
コールがあれば、30分以内に駆けつけられるエリアを範囲として「日常生活圏域」を設定し、地域包括支援センター(ブランチを含む。)を整備し、在宅サービスの充実を図ることで、特別養護老人ホーム等の介護施設に入所しないで、地域で暮らし続ける仕組みを作ろうとする試みです。
その実現に向けた第5期介護保険事業計画の策定であり、その計画を実現するための、各種サービスの創設・整備となっています。
第5期介護保険事業計画の作成に当たっては、各日常生活圏域ごとの詳細なニーズ把握が求められるところです。また、関連して、そのニーズに対してサービスを提供する事業者について、地域密着型に関しては、従前の自由参入から公募制へと切り替えることで参入制限を図れる仕組みとなっています。併せて、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの普及を図ることで、これまで要件を満たせば自由に参入が可能であった訪問介護等の指定について、事前の区市町村との協議を必要とするように、考え方の転換を図っています。
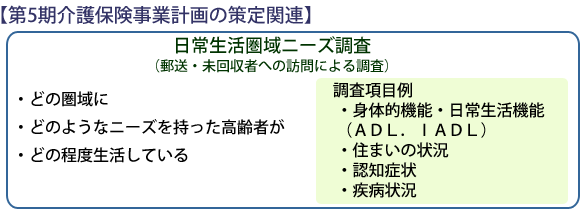
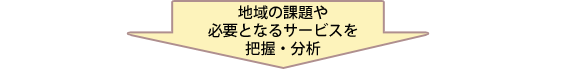
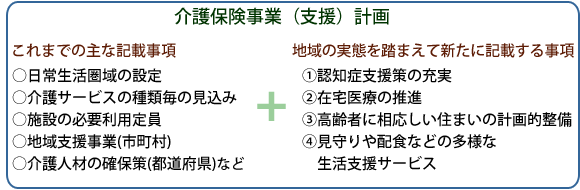
注:新たに記載する事項について、1.については予算化して体制構築、2.については地域の医療資源の確認とネットワーク構築、3.については「サービス付き高齢者住宅」以外に増殖している多様な形の「高齢者が住んでいる(集めている)アパート・住宅」をどのように評価するのか、しないのかの課題、4.については地域包括ケアの中心的テーマの一つである「崩壊したコミュニティの再生」といった大きな課題を抱えています。形式的・アリバイ的計画化では、地域の抱えている課題を糊塗するだけで、禍根を残しかねません。

