6.入浴を支える福祉用具
高齢者の入浴を支えるために、様々な用具がありますので、その種類と活用法について紹介します。
(以下の福祉用具類は、形状等をご覧いただくためのもので、あくまで例示として掲載しています。)
1.浴槽
浴槽は、出入りがし易く浮力を調節しやすいものがよいでしょう。浴槽の縁の高さは、椅子の高さと同じくらいの概ね40センチ。深さは50センチくらいが出入りや浮力の調節がしやすく、また、浴槽の内寸は100センチ程度で側面が斜めになっていない方が浮力の調節に適しています。浴槽内に手すりが設置されたものもあります。
2.すのこ・滑り止めマット

すのこ

吸盤式滑り止めマット
3.手すり(壁面用・浴槽用)
壁面用
手すりの表面の形状は、握力がなく、濡れた手で触れても滑らないように、波形になっているものがよいでしょう。

縦型手すり

L型手すり

表面が波形になった手すり
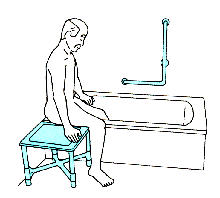
浴槽脇のL型手すり
浴槽用
浴槽の縁に固定し、主に立位による浴槽の出入りの際の補助に使用します。しっかりと固定されているか、その都度確認をした上で使用します。浴槽の構造によっては、取り付けられない場合があります。

浴槽固定手すり

浴槽内でも使用できる手すり
浴槽内の手すりは、浴槽内の姿勢保持と浮力の調節に使用します。
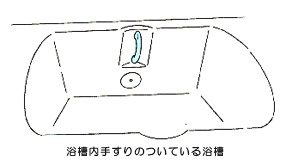
浴槽内手すり

浴槽固定式の浴槽内手すり
4.シャワーチェア
シャワーチェアは、身体を洗う際に座位を安定させるために使用します。様々な種類がありますが、座位保持の能力によって選択します。座位保持能力が低い場合には、背もたれや肘掛け付きのものを利用します。座面の形状もフラット(平ら)、湾曲、クッション、穴あきなどがあります。座面がフラットなものは、移乗台の代わりなど多用途に使用できる利点があります。また、座面がターンテーブル(回転する)ものもあり、浴槽への出入りなどの際は便利です。湾曲タイプは、座位を安定させるものですが、座面の中央にしっかりと座らないと、かえって不安定になります。穴あきタイプは、陰部などを洗いやすい反面、姿勢保持機能の高さが要求されます。介助スペースを確保や家族が入浴するときなど、必要がないときに折りたためるものもあります。 座面の高さは、使用の状況により調整します。身体を洗うことを中心に考えるのであれば、足裏が床に、大腿部が座面にしっかりと着き、安定した姿勢を保持できる高さにします。また、立ち上がりの補助を重視するのであればやや高めに、浴槽への出入りに使用するのであれば、浴槽の縁の高さにあわせます。 立ち座りの際、肘掛けや座面に手をついて行う場合は、シャワーチェアの脚が座面よりも広く開いたものにしましょう。タイプによっては、転倒の危険性があります。

座面が平らなもの

座面にターンテーブルがついたもの

背もたれや肘掛けがついたもの

肘掛けをはずしたところ

高さ調節ができるもの

穴あき式のもの

折りたたみ式のもの
5.バスボード、浴槽台、ベンチバスターなど
バスボード
脱衣場や浴室内の壁面に固定しますが、様々な形状や設置の方法があります。立ち上がりや大きな段差があるときには縦型の手すり、移動の補助や姿勢を安定させるときには横型の手すりを設置するなど、使用の状況や場所に応じて使い分けるようにします。浴槽の脇に設置する場合にはL型が一般的です。設置の位置を決める際は、必ず試行してから決め、木ねじや接着剤でしっかりと固定しましょう。

バスボード
浴槽内台
浴槽が深くて、浴槽から出にくい場合や、膝や股関節が曲がりにくい場合などに、浴槽内に置いて使用します。また、浴槽の長さが長いときには、浴槽内の端に横向きに置き、足で突っ張れるようにして、浮力の調整を行います。浴槽内台の脚は吸盤などでしっかりと固定できるものが良いでしょう。

浴槽内台

浴槽内台を使用したところ
ベンチバスター

浴槽取り付け型チェア
福祉用具の利用について
介護保険では、福祉用具のレンタルや販売について「福祉用具の貸与(介護予防福祉用具の貸与)」、「特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)」といったサービスを実施しています。「福祉用具の貸与」では、車いすや特殊寝台(ベッド)など、12品目につき利用できますが、そのうち要支援1・2の方から利用できる「介護予防福祉用具の貸与」では、手すりの貸与も行っています。
また、「特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)」では、レンタルになじまない排泄や入浴に使われる用具の購入費が支給されます。要介護状態区分に関係なく限度額は1年間(4月1日から3月31日まで)10万円です。登録された事業者に購入費をいったん全額支払った後に、限度額の範囲内でかかった費用の9割が支給されます。東京都から「特定福祉用具販売」の指定を受けた事業者から購入することになります。
さらに、「住宅改修(介護予防住宅改修)」といった介護保険のサービスもあります。
介護保険適用の対象となっている方が、廊下や階段、浴室への手すりの設置、段差の解消、など小規模な改修を行った際にその費用の一部が支給されます。要介護状態に関係なく限度額は原則一回限りで20万円です。
全額自己負担で住宅改修を行い、支払った費用(上限20万円)の9割を払い戻す(償還払い)方式です。この手続きには、申請書のほか、住宅改修理由書などの書類が必要となりますので、改修を行う前に、区市町村の介護保険窓口にご相談下さい。なお、区市町村によっては、住宅改修の事業者を指定しているところもあります。
参考文献
- 高齢者・障害者の生活をささえる福祉機器Ⅲ(入浴、排泄、自助具、衣服)
- (財)東京都福祉保健財団 《旧 (財)東京都高齢者研究・福祉振興財団》 発行

