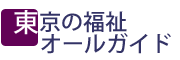介護保険制度の仕組み
介護保険制度の仕組み
介護保険制度は、介護を必要とする状態となってもできる限り自立した日常生活を営み、人生の最後まで人間としての尊厳を全うできるよう、介護を必要とする人を社会全体で支え合う仕組みです。平成12年4月に施行して以来、在宅サービスを中心に利用が急速に進み、今後、介護を必要とする高齢者や認知症の高齢者の一層の増加が見込まれています。
利用者は自らの選択に基づいてサービスを利用することができ、介護に関する福祉サービスと保健医療サービスが総合的・効率的に提供され、公的機関のほか、株式会社やNPOなど多様な事業者の参入促進が図られ、効率的にサービスが提供される仕組みとなりました。
介護保険制度は、将来にわたって安定的な運営を確保しながら、介護・医療・住まい・生活支援・介護予防が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の更なる深化・推進を図るため、順次見直しが行われてきています。
保険者(実施主体)
介護保険の実施主体である保険者は、区市町村です。要介護認定、保険給付、第1号被保険者の保険料の賦課・徴収などの保険事業の実施や介護サービスの基礎整備などを行い、介護給付費の12.5%を負担しています。
被保険者(保険に加入する人)
区市町村の区域内に住所を有する40歳以上の人が、その区市町村の被保険者となります。
- 第1号被保険者 65歳以上の人
- 第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
介護保険料
- 第1号被保険者の保険料は、老齢退職年金・遺族年金または障害年金を年18万円以上受けている人は、特別徴収として年金から天引きが行われ、それ以外の人は、普通徴収として個別に徴収されます。
- 第2号被保険者の保険料は、医療保険料とあわせて徴収されます。
保険給付(サービス)が受けられる人
寝たきりや認知症などで常時介護を必要とする状態(要介護者)や、日常生活を営むのに支障がある状態(要支援者)になった場合に介護サービスを受けることができます。
65歳以上の第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わず給付が受けられます。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、老化に伴う16種類の特定疾病が原因である場合に限られます。16種類の特定疾病とは、
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- 後縦靭帯骨化症 (こうじゅうじんたいこっかしょう)
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症(ウエルナー症候群)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
- 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険の財源構成
介護保険事業の財政は、利用者負担金と公費で賄います。 負担割合は、以下のとおりです。
- 利用者負担金 10%
- 公費と保険料で90%(内訳は以下のとおりです。)
- 国 25%
- 都 12.5%
- 区市町村 12.5%
- 第1号被保険者 22%
- 第2号被保険者 28%
介護保険の申請からサービス利用まで(要介護認定)
介護保険の給付を受けるためには、被保険者は、区市町村に申請し要介護認定を受ける必要があります。 認定は、原則として申請日から30日以内に行われます。
サービス利用料
- 介護サービスを利用した場合は、要した費用の1割(一定以上の所得を有するかたは2割又は3割)を利用料として自己負担します。なお、介護サービス計画の作成などの費用は、全額が保険給付され自己負担はありません。
- 介護保険の対象となっている福祉用具の購入費や、住宅改修費は、定められた支給限度額の範囲内で、費用の一部の払戻しが受けられます。
- 施設に入所した場合や通所して介護サービスを利用した場合は、1割(または2割・3割)の自己負担の他に食費と居住費、理美容代などの日常生活費を負担します。
- 1割(または2割・3割)の自己負担が世帯合計で1か月44,400円の上限額を超えた場合は、高額介護サービス費として、超えた分が払い戻されます。低所得者については、その所得に応じた上限額が設定されています。
- 医療保険の一部負担金の額と介護保険の利用者負担額の年間合計額が一定の限度額を超えた場合は、超えた分が払い戻されます。
給付の調整
介護保険による給付は、医療保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、障害者総合支援法などの他の法令等による給付に優先し、同一人が重複して給付を受けられません。ただし、一部例外があります。
介護保険で利用できるサービス
苦情対応窓口
介護保険にはサービスに対する苦情処理の仕組みがあります。事業者との話し合いだけでは解決できない問題は、まず区市町村の介護保険担当窓口で相談します。それでも解決が難しい場合は国民健康保険連合会に相談します。
国保連合会は、介護保険法第176条第1項第2号に基づく介護保険サービスの質の向上に関する調査及び指定事業者への指導・助言などの苦情処理を行います。
区市町村の介護保険窓口
東京都国民健康保険連合会 介護サービス苦情相談窓口
※外部のページへリンクしています。このページに戻る場合は、ブラウザの「戻る」機能をご利用ください。
東京都介護保険制度相談窓口 03−5320−4597
(月曜日から金曜日 午前9時から12時・午後1時から午後4時30分)
根拠法令
介護保険法