5.浴槽への出はいりについて
浴槽への入り方、浴槽内での姿勢の確保、浴槽からの立ち上がり
浴槽への出入りは、立位の場合は手すりに掴まり身体を安定させながら行いますが、高齢者の場合は、なるべく座って出入りした方が安心でしょう。特に一人暮らしの場合などは、転倒などの危険性を考えると、立位での浴槽の出入りは避けたいところです。足の筋力は、30歳代をピークに、高齢者になると健康な場合で約7割まで落ちると言われています。しかし、立位のバランスは約3割にまで落ち込んでしまうとのことです。高齢者に転倒が多いのは、筋力の低下はもちろんですが、立位バランスの低下が大きな影響を与えています。
特に立位により片麻痺の方が浴槽へ入る際は、非麻痺足(ひまひそく:麻痺のない方の足)から入るのが原則です。その理由は、非麻痺足側であれば、浴槽に張られたお湯の温度が確かめられることや、浴槽内で足の踏ん張りが効くということがあげられます。また、浴槽から出る場合も同様に、なるべく非麻痺足から出ます。しかし、入る時とは反対向きで出ることになり、手すりも浴槽の両脇につけるなどの対応が必要になる場合があります。
立位で浴槽へ入る場合
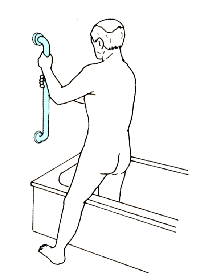 ←立位での浴槽への入り方
←立位での浴槽への入り方
浴槽固定式の手すりを利用する場合
 浴槽用手すりは、浴槽にしっかり固定して使います。
浴槽用手すりは、浴槽にしっかり固定して使います。
 立位ではいる場合は、手すりを使って身体を安定させて入ります。膝などの関節が曲がりにくいときは使いにくいこともあります。
立位ではいる場合は、手すりを使って身体を安定させて入ります。膝などの関節が曲がりにくいときは使いにくいこともあります。
 浴槽内の手すりで、身体を安定させます。
浴槽内の手すりで、身体を安定させます。
座って浴槽へ入る場合
座って浴槽へ出入りする場合には、シャワーチェアやバスボードなどを使います。シャワーチェアや移乗するための台を浴槽の横に置き(浴槽の縁と高さもあわせる)、座ったまま身体を回転させて片足ずつまたいでいきます。シャワーチェアや移乗の台は座面がフラット(平ら)の方が出入りがしやすいでしょう。
シャワーチェアを利用した場合
 シャワーチェアの座面の高さを浴槽の縁にあわせ、なるべく浴槽側に座ります。
シャワーチェアの座面の高さを浴槽の縁にあわせ、なるべく浴槽側に座ります。
 片足ずつ浴槽に入れます。
片足ずつ浴槽に入れます。
 臀部を浴槽の角にずらします。
臀部を浴槽の角にずらします。
 ゆっくりと浴槽内にしゃがんでいきます。
ゆっくりと浴槽内にしゃがんでいきます。
バスボードを利用した場合
また、上述の動作が難しい場合には、バスボードを使います。バスボードを浴槽の縁に渡して、シャワーチェアなどからバスボードに臀部を移動させながら片足ずつ浴槽に入れていきます。
 バスボードを浴槽に渡し、シャワーチェアからバスボードに臀部を移動させます。
バスボードを浴槽に渡し、シャワーチェアからバスボードに臀部を移動させます。
 片足ずつ浴槽に入れ、バスボードにのせた臀部を浴槽の中央付近まで移動させます。
片足ずつ浴槽に入れ、バスボードにのせた臀部を浴槽の中央付近まで移動させます。
 立ち上がり、介助者にバスボードをはずしてもらいます。
立ち上がり、介助者にバスボードをはずしてもらいます。
 ゆっくりと浴槽内にしゃがんでいきます。
ゆっくりと浴槽内にしゃがんでいきます。
浴槽に入る際には、バスボードを本人あるいは介助者が一旦取り外しておかなければなりません。また、あまりボードに厚みがあると、浴槽の底に足が着きにくくなることも考えられます。そのため、バスボードはなるべく薄くて軽いものがよいでしょう。跳ね上げ式で格納されるものもあります。
浴槽取り付け型チェアを利用した場合
バスボードの脱着が困難な場合には、浴槽取り付け型チェアを浴槽の縁に設置する方法もあります。ただし、浴槽取り付け型チェアだけでは身体が不安定なため、手すりの設置も合わせて考える必要があります。
 浴槽取り付け型チェアは浴槽にしっかりと固定します。
浴槽取り付け型チェアは浴槽にしっかりと固定します。
 身体を安定させるため、手すりを活用しましょう。
身体を安定させるため、手すりを活用しましょう。
 臀部を回転させながら片足ずつ浴槽に入れます。
臀部を回転させながら片足ずつ浴槽に入れます。
 手すりを使いながら、ゆっくりと浴槽内にしゃがんでいきます。
手すりを使いながら、ゆっくりと浴槽内にしゃがんでいきます。
浴槽は、出入りのしやすさからやや大きめのものがよいでしょうが、浴槽内で姿勢が安定するためには、浴槽の端に足が届き、しっかり支えられるくらいのものがよいでしょう。深さもあまり深すぎると浮力で身体が浮き、溺れてしまうなど危険な場合があります。浴槽内で姿勢を保持するためには、浴槽内の手すりも有効です。また、浴槽内でも、滑り止めマットを使用すると、出入りのときにも安心です。滑り止めマットは、床の材質が滑りやすいものの場合には、脱衣室、洗い場、浴槽のそれぞれに敷くとよいでしょう。
 *浴槽内に滑り止めマットを敷くと、浴槽への出入りや浴槽内の姿勢も安定します
*浴槽内に滑り止めマットを敷くと、浴槽への出入りや浴槽内の姿勢も安定します
浴槽から出る場合(座位)
浴槽から出る場合は、浮力も利用しながら立ち上がりますが、足をできるだけ引き寄せた後、身体を前方に傾けて縦手すりを使いながら立ち上がります。シャワーチェアを利用して出る場合は、立ち上がったあと浴槽の角に座り、足を片方ずつ出して臀部をシャワーチェアの方にずらしていきます。また、バスボードを利用する際は、立ち上がったところで介助者がバスボードをセットします。
▼シャワーチェア、バスボード、浴槽取り付け型チェアを使って浴槽から出る様子
(浴槽から立ち上がるまでは、共通の動きです。)
 足を臀部の方に引き寄せます。
足を臀部の方に引き寄せます。
 身体を前に傾けるために頭を前方にもっていきます。
身体を前に傾けるために頭を前方にもっていきます。
 縦型の手すりを使って身体を引き上げるようにして立ち上がります。横型の手すりがある場合は立ち上がったあとに持ち替えます。
縦型の手すりを使って身体を引き上げるようにして立ち上がります。横型の手すりがある場合は立ち上がったあとに持ち替えます。
ここからの動きは、利用する福祉用具によって異なります
シャワーチェアの場合
 浴槽の角あるいは縁に腰掛けます。
浴槽の角あるいは縁に腰掛けます。
 片方ずつ足を出します。
片方ずつ足を出します。
 臀部を移動させてシャワーチェアに座ります。
臀部を移動させてシャワーチェアに座ります。
バスボードの場合
 立ち上がったら介助者がバスボードを浴槽に渡します。
立ち上がったら介助者がバスボードを浴槽に渡します。
 バスボードに座って、臀部をシャワーチェアの方にずらしていきます。
バスボードに座って、臀部をシャワーチェアの方にずらしていきます。
 片方ずつ足を出し、シャワーチェアに座ります。
片方ずつ足を出し、シャワーチェアに座ります。
浴槽取り付け型チェアの場合
 立ち上がったら手すりで身体を安定させながら浴槽取り付け型チェアに座ります。
立ち上がったら手すりで身体を安定させながら浴槽取り付け型チェアに座ります。
 臀部を回転させながら、片方ずつ足を出します。
臀部を回転させながら、片方ずつ足を出します。
 状況に応じてシャワーチェアに移ります。
状況に応じてシャワーチェアに移ります。

