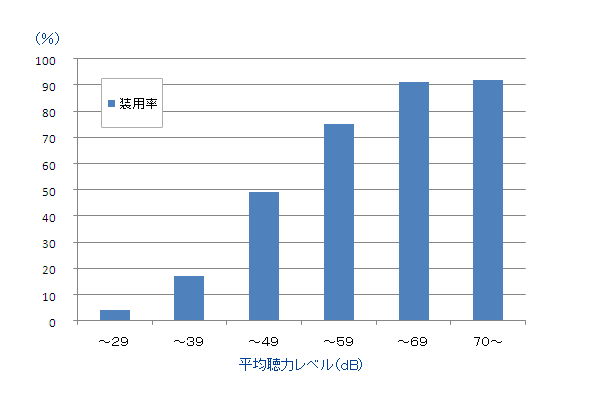1.「聞こえ」が悪くなったら
1.聞こえのしくみ
私たちの周囲には、様々な音や音声があります。私たちは、聴覚を通して、身の回りの音や音声から、周囲の様子や様々な情報を受け取り、コミュニケーションを行っています。 聞こえが悪くなるということは、これらの音や音声による情報入手やコミュニケーションが順調に行えなくなるということです。 では、音はどのようにして私たちに聞こえてくるのでしょうか。 図をご覧ください。 音は、空気を伝わって、耳介から外耳道を通り鼓膜を振動させます。振動は、鼓膜から鼓膜の内側の中耳にある耳小骨を伝わって内耳に届きます。内耳には、聴細胞があり中耳からの振動を分析して感じ取ります。そして、信号として、聴神経に伝わり、大脳へと送られて、音や音声として理解されるわけです。 外耳から中耳までは「伝音系」の働き、内耳から大脳までは「感音系」の働きと分類します。
音とことばの聞こえのしくみ
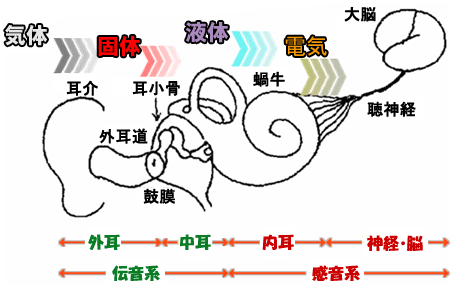
2.難聴の人の『聞こえ』について
難聴は、聞こえのしくみのどこかの機能が低下することにより、生じる障害です。難聴の原因となる部分がどこの働きの不都合かによって、難聴の種類が分かれ、聞こえ方が異なります。
| 伝音性難聴 | 感音性難聴 | 混合性難聴 | |
|---|---|---|---|
| 障害が生じた場所 | 伝音系 | 感音系 | 伝音系と感音系の両方 |
| 音の聞こえ方 | 音が小さく聞こえる | 音が小さく聞こえる上に、歪み響いて不快感を伴う | 伝音性難聴と感音性難聴の両方の特徴 |
| 言葉の聞こえ方 | 音を大きくすれば聞き取れる | 音を大きくしてもはっきり聞き取れない |
聞こえの障害は、大きく分けて二つの障害があります。聴力(音の大きさ)の障害と聞き分け(音が歪み響いて音やことばの弁別が出来ない)の障害です。 伝音性難聴は聴力の障害で感音性難聴は聴力と聞き分けの両方の障害ということが言えます。
伝音系のみの障害の場合、聴力は最大で70dBを超えることはありませんので、補聴器で音を大きくすることで、音やことばが良く聞こえ、聞き取れるようになります。補聴器の調整はそれほど困難ではありません。骨伝導のものも、伝音性難聴には有効です。
感音系の場合は、伝音系が聴力低下には限度があるのに対して、完全に聞こえなくなるまで低下します。聞こえが残っている場合は“聞こえ”に対しては補聴器である程度改善できますが、ことばの聞き分けや聞き取りは、その人の聞こえ方に合わせた細かな調整をしても限界があります。
3.難聴に気がついたら
耳鼻科医の診察を受けて、聞こえの状態を知りましょう。
- 耳鼻科医の診断 : 難聴の原因、治療、難聴への対応等の助言を受けます
- 補聴器の相談 : 耳鼻科医より補聴器の可否、選択、適合、装用等の指示、助言(処方)を受けます
- 補聴器の購入 : 耳鼻科医から、認定補聴器技能者のいる認定補聴器専門店(いずれもテクノエイド協会認定)を紹介してもらい購入しましょう
*聴力検査(オ−ジオグラム)の結果は必ずもらいましょう。聴覚の管理、補聴器の選択・適合のときに使います。
聴力図(オージオグラム)の見方を覚えましょう。
縦軸の数字は、聴力レベル(音の大きさ・デシベルdB)で聞こえの度合いを表します。
「0」が初めてかすかに聞こえる値(最高値)で数字が大きくなるほど大きな音しか聞こえなく、聞こえが悪いことになります。
横軸の数字は、周波数(音の高さ・ヘルツHz)を表し、125Hzは低い音、8000Hzはキーンという高い音を表します。
つまり、聴力図とは各周波数(それぞれの音の高さ)でどのくらい聞こえるのか、ヘッドホンをつけて検査(オージオメータ)した結果の図です。○印(赤)は右耳、×印(青)は左耳の聞こえの値です。
聴力図 (オージオグラム)の見方
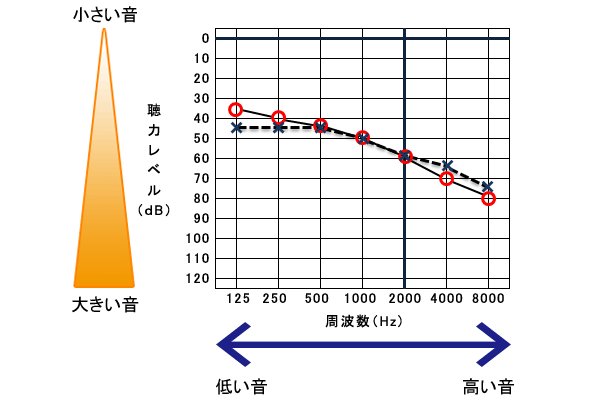
聴覚障害の程度と分類
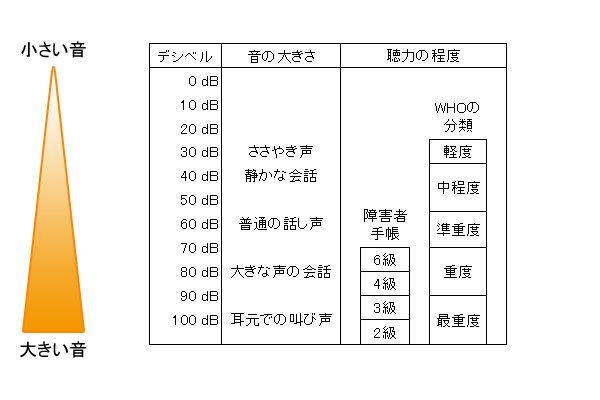
障害手帳の認定の対象は、聴力レベルが平均70dB以上、かつ、語音明瞭度(単音の聞き分け)が50%以下で補聴器の支給がありますが、日常の会話に支障を感じる40dB以上の方から補聴器の装用を考える方が多いようです。(2001から2011年“聞こえと補聴器の相談会”に参加した人のデータより)
補聴器装用耳の平均聴力レベル別装用率
| 聴力レベル(dB) | 〜29 | 〜39 | 〜49 | 〜59 | 〜69 | 70〜 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装用率 | 4% | 17% | 49% | 75% | 91% | 92% | |
| 装用者数 | 3人 | 29人 | 98人 | 106人 | 70人 | 97人 | 403人 |
| 非装用者数 | 67人 | 138人 | 101人 | 36人 | 7人 | 9人 | 358人 |
| 合計人数 | 70人 | 167人 | 199人 | 142人 | 77人 | 106人 | 761人 |