 介護給付費の区分限度額について
介護給付費の区分限度額について
次に、平成21年度に介護報酬単価が引き上げられましたが、要介護度別の区分限度額の引き上げが行われなかったため、介護保険のサービスの上限を超える要介護者の発生が想定されました。これを受け、事業者団体等からは上限額の引き上げの要望等が提出され、厚生労働省において検討をしてきた結果が社会保障審議会で公表されました。明確な結論付けはなかったのですが、以下のようにまとめられました。
ここからみると、結論は多論表記となっていますが、ケアプランを見直すことで限度額で対応できる、ゆえに引き上げは必要ない、というトーンのように思えます。
「介護給付費分科会平成23年2月7日資料1から」
|
||
1 費用
具体的に利用者について考えてみると、まず保険料等費用ですが、これはこの間喧伝されていたように、「このままでは5,000円を超える」とのキャンペーンのとおり、現行の全国平均の4,160円よりは確実に上昇することが見込まれています。ではいくらになるかについては、これからの制度設計にかかっています。今後、保険者による詳細な地域のニーズ調査、それに基づき国の整備指針等に基づく第5期介護保険事業計画を策定する過程で、最終的な保険者ごとの第1号被保険者の保険料が決まります。
1割の自己負担分については、訪問系サービスは1割負担ですが、通所系では食事その他日用品費の自己負担があり、既に1割を超えています。グループホームでは、利用者負担の平均が18万~20万円程度といわれており、事実上総事業費の4割以上の負担となっています。特別養護老人ホームの利用者負担についても、個室や食費負担等を含めると3割を超えていると思われます。
今後、介護保険以外の有償サービスを積極的にケアプランに位置付けるようになれば負担は現在よりも増すことになります。
これをどう評価するかは、人により異なると思います。少子・高齢化と財政難に着目すれば、「やむを得ない」との考え方が主流と思われますし、セーフティーネットあるいは「福祉国家」という観点からは、世界的にも低水準と思うでしょうし、その辺りは視点によって異なると思われます。
2 使い勝手(今よりサービスが多く使えるか)
サービス総量が要介護認定者の増加に比例する程度で、それ以上の増加がない中では使い勝手が劇的に良くなるということは考えにくいのが現状です。ただし、介護保険サービスやその他のサービスを活用して暮らしを支えるという「地域包括ケアシステム」が機能し、その上でサービス付き住宅や24時間の訪問介護サービスがあり、それらを訓練された「ケアマネジャー」が上手に使いこなすスキルを獲得していれば、相当の改善も期待されるのではと思われます。
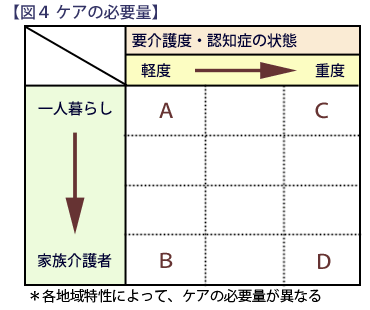 図4は簡単なマトリックス図ですが、要介護度・認知症の状態地域によっても違うという前提の下で軽度重度あっても、例えば要介護度が軽くても、AとBでは暮らすためのケアは異なります。
図4は簡単なマトリックス図ですが、要介護度・認知症の状態地域によっても違うという前提の下で軽度重度あっても、例えば要介護度が軽くても、AとBでは暮らすためのケアは異なります。
例えばAの場合、要介護者の年齢、性格、認知度によっても本人の「生活力」は大きく異なります。一般的にはAよりもCの方が、入所施設の必要度が
多いといえても、個別の事例としては逆もしばしばあることは、現場では周知のことです。
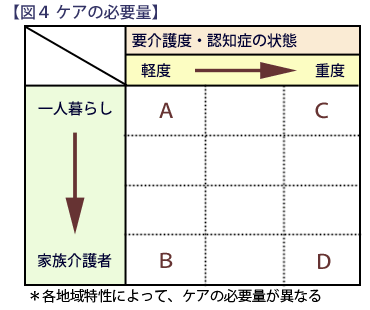 図4は簡単なマトリックス図ですが、要介護度・認知症の状態地域によっても違うという前提の下で軽度重度あっても、例えば要介護度が軽くても、AとBでは暮らすためのケアは異なります。
図4は簡単なマトリックス図ですが、要介護度・認知症の状態地域によっても違うという前提の下で軽度重度あっても、例えば要介護度が軽くても、AとBでは暮らすためのケアは異なります。

