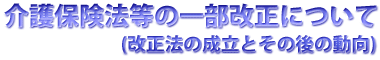4 その他
(1)介護予防・日常生活支援総合事業について
旧特定高齢者に対する介護予防と、要支援1.2の者に対する介護予防を統合し、そこに厚生労働省が定める基準に合致した配食サービスや見守りサービス等を加えた新たな分野として「介護予防・日常生活支援総合事業」が創設されます。そのサービスを「地域包括ケアシステム」における軽度者への新しいサービス提供の形として活用すると思われます。その意義は、介護保険サービスに、追加の有償家事援助サービスやボランティア等をケアミックス(ソーシャルインクルージョン)として位置づけて、参加型社会保障実現の第一歩として創設されたものと思われます。
介護予防・日常生活支援総合事業-
新サービスでは、サービスの一層の総合化の実現が可能
要支援の認定者に対するサービスが、介護保険の介護予防サービスに加えて配食サービスや見守りサービスとセットで供給できる体制となる(下図1~3)。 - 本事業の実施は区市町村の判断によるが、費用負担面からは、地域支援事業で行っていた事業が、一部介護保険の財源負担に移行するため、区市町村にとって有利となる。
- ケアマネジメントの観点からは、新たに日常生活支援総合事業に対応したケアマネジメントが必要となり、より複雑化する可能性がある(下図A~C)。
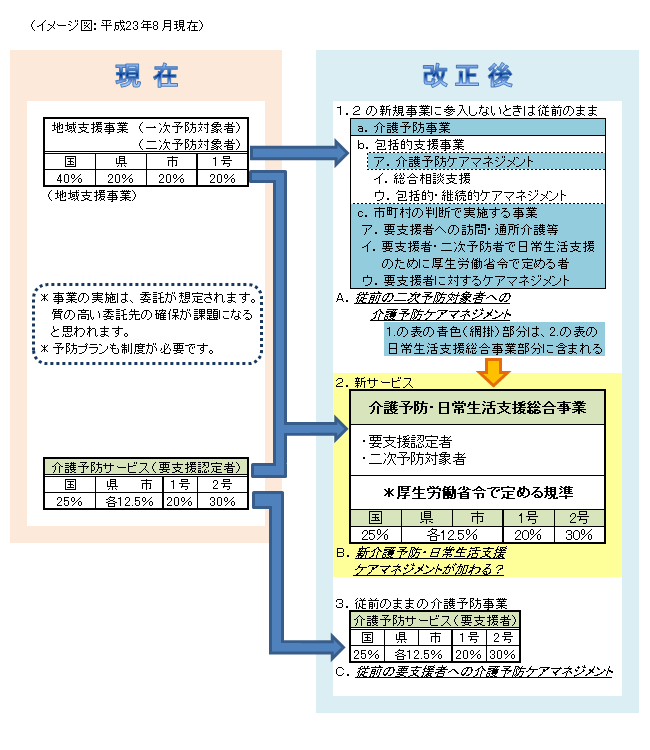
(図長谷作成)
※ 第五期の被保険者の保険料負担割合は、1号21%、2号29%の予定
※ 「国、県市、1号、2号」は、それぞれの介護保険の費用負担の割合を表す
(2)制度改正に向けた取組
- 運営イメージ
- 市町村の判断により、要支援者・介護予防事業対象者向けの介護予防・日常生活支援サービスを総合的に実施できる制度を創設。事業を導入した市町村は、市町村・地域包括支援センターが、利用者の状態像や意向に応じて、予防給付で対応するのか、新たな総合サービスを利用するのかを決定
- 利用者の状態像や意向に応じて、介護予防、生活支援(配食、見守り等)、権利擁護、社会参加を含めて、市町村が主体となって総合的で多様なサービスを提供
- 利用者像
- 要支援と非該当を行き来するような高齢者に対し、総合的で切れ目無いサービスを提供
- 虚弱、引き籠もりなどの介護保険利用に結びつかない高齢者に対し、円滑にサービスを導入
- 自立や社会参加意欲の高い者に対し、社会参加や活動の場を提供
等が想定されています。
(参考)
| 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(平成二十三年五月二十七日 衆議院厚生労働委員会ほか) | ||
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
- 介護職が喀痰吸引等を実施するに当たっては、知識・技術の十分な習得を図るとともに、医師、看護師その他の医療関係者との連携のもとに、安全管理体制を整備し、その上で実施状況について定期的な検証を行うこと。
- 介護職員等の処遇改善については、財源を確保しつつ、幅広い職種を対象にして実施するよう努めること。特に、介護領域における看護師の重要な役割に鑑み、介護保険施設や訪問看護に従事する看護師の確保と処遇改善に努めること。
- 介護サービス情報の公表制度については、適正な調査が実施されるよう、都道府県、指定情報公表センター、指定調査機関その他の関係者の意見を十分に踏まえつつ、ガイドラインの作成等必要な措置を講ずること。その際、事業者より申出がある場合には積極的に調査できるよう配慮するとともに、指定調査機関・調査員の専門性を活用すること。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護や複合型サービスについては、医師、看護師、介護職員間の司令塔づくりを含め、円滑な実施体制の実現を図ること。
- 介護予防・日常生活支援総合事業については、その創設においても要支援認定者が従来の介護予防サービスと同総合事業を選択・利用する意思を最大限尊重すること。また、国として財源を確保し、各市町村のニーズに応じて適切に実施するよう努めること。
- 介護療養病床の廃止期限の延長については、三~四年後に実態調査をした上で、その結果に基づき必要な見直しについて検討すること。
- 認知症対策を推進するため、地域における医療、介護等の緊密な連携を図るとともに、市民後見人の活用を含めた成年後見制度の周知・普及を図り、権利擁護の体制整備を促進すること。
(上記、一から六の表現は、衆議院と参議院でそれぞれ異なる場合もある。)
参議院附帯決議で追加された項目
その他の関連特集記事
- 平成23年2月~4月掲載
「介護保険法の改正」について - 平成24年6月~(連載中)
介護保険法の改正後の動向について