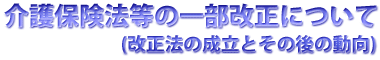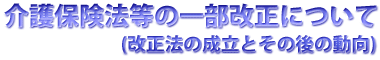
3 法改正後の施行に向けた取組み
(1)「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的指針」の改正案の提示
- これは各自治体が「第5期介護保険事業計画」策定するのための基本指針の一部改正です。主なポイントは次のとおりです。
- 基本的理念等
- 地域包括ケアシステムの構築
- 孤立化のおそれのある高齢者単身・夫婦のみ世帯に対する生活支援の留意
-
介護給付等対象サービスのあり方に関する目標
団塊世代が高齢者となる2015年、後期高齢者となるその5年後、10年後、あるいは各自治体が高齢化のピークとなる時期をにらみ、目指すべき地域包括ケアシステムの構築を目標にする。
- 市町村介護保険事業計画
- 要介護等の実態の把握
- 居住に関する事項を定める計画との調和
- 基本構想との調和規程の削除
- 介護給付等対象サービスの見込み量及び見込み量確保のための方策
- 包括的支援事業の委託にあたっての実施方針の明示
- 今後地域で必要と考えられる4事項について、各自治体が地域の実情に応じ、優先すべき重点事項を選択して取り組むことができるよう計画に追加
- 認知症支援策の充実
- 医療との連携
- 高齢者の居住に係る連携
- 生活支援サービス
- 地域支援事業に要する費用の額並びに量の見込み量及び見込み確保のための方策 ほか
- 介護予防・日常生活支援総合事業の追加(多様な人材や社会資源の有効活用)
(2)制度改正に向けた取組
- 地域包括ケアシステムの導入や、介護予防・日常生活支援総合事業等の実施のためには地域と連携し、社会資源を活用した居宅サービス計画づくりと、チームケアの実体化が求められます。
- 介護保険制度の実施の要は、介護支援専門員が担う「ケアマネジメントシステム」であることは間違いありません。ただ、ケアマネジメントが不十分でも優秀な現場であれば、それを繕いながら利用者サービスの向上を図っています。
- 現在、ケアマネジメントの見直しの検討が行われているようですが、従事者や利用者の実態に即した、簡潔で分かりやすい仕組みとすることが求められています。
- その前提として、ケアマネジメントの現状の冷静な検証が重要です。実態の検証なしに、あるべき論で理論を組み立てることは百害あって一利なしといえます。
- 私見ですが、事務受託法人として居宅介護支援事業所やサービス事業所の実態をみると、一部で優秀な事業所もありますが、ほとんどは「給付管理型ケアマネジメント」の状態にあるように思えます。利用者等の意向を正確に把握し、その個別性を踏まえたケアプランとなり、かつ、サービス担当者会議で必要な議論行われ、問題が共有された居宅サービス計画が作成されているかと言えば、心許ない状態と思われます。
- また、医療連携が重視される中、介護支援専門員の従事者の比率は、下表のように変化しています。
| |
看護師等 |
社会福祉士 |
介護福祉士 |
ヘルパー |
その他(医師・薬剤師等) |
| 平15年 |
37.6% |
6.5% |
32.6% |
12.8% |
10.4% |
| 平21年 |
22.9% |
7.0% |
50.0% |
14.9% |
5.2% |
(*三菱総研「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員勤務の実態に関する調査報告書/平成21年老人保健健康増進等事業)
平成20年に行われた東京都の調査でも同様な傾向が見られると共に、在職期間の平均が4年と短い上に介護支援専門員の年齢構成の高齢化(50歳以上がほぼ半数)が進んでいます。
- 24時間定期巡回・随時対応訪問介護看護についても、効果の検証やケアマネジメントシステムの検討がモデル事業として各地で行われています。
- これらの新サービスやシステムのモデル事業のまとめや検討結果(10月末予定)を受け、指定基準の改正が行われると思われます。それに引き続き、あるいは同時期に医療の診療報酬の改定と介護報酬の改定が行われる見込みです。