平成19年度東京都福祉サービス評価推進機構評価者養成講習募集
この評価者養成講習は、都における福祉サービス第三者評価を行うために必要な一定のレベルの知識や経験がある方を対象に、その知識や経験があることを前提として、東京都福祉サービス第三者評価のルールの理解や、評価の視点や判断基準の共有化を図ること等により、都民や福祉事業者等から信頼される評価を行える評価者を養成することを目標としています。
東京都福祉サービス評価推進機構が規定する「福祉サービス第三者評価機関認証要綱」の第2条第9号において、"評価者は「評価を行うのに必要な資格や経験を有し、機構が実施する評価者養成講習を修了し、必要なフォローアップ研修を受講している者で、かつ機構が公表する名簿に登載されている者」"と示されています。
この講習を修了することは、評価者となるための必要条件の一つとなっています。
つきましては、以下のとおり、受講者を募集することといたしましたので、お知らせします。
Ⅰ 講習日程・場所等
1.養成講習カリキュラム
養成講習講義カリキュラム(予定)
| 科目 | |
| 1日目 |
◆オリエンテーション ◆第三者評価概論 ◆評価の枠組み及び事業評価について ◆評価実施方法の理解について ◆評価のまとめ方及び評価結果報告書の作成方法について ◆振返り問題 |
| 2日目 |
◆福祉サービスの基本的理解について ◆利用者調査について ◆事業プロフィルについて ◆各カテゴリーの関連について ◆振返り問題 ◆ケーススタディ概要説明 |
| 3日目 | ◆ケーススタディ⇒利用者調査及び事業プロフィル・各分析シートの理解(グループ作業) |
| 4日目 | ◆ケーススタディ⇒訪問調査までの事前分析の理解(グループ作業) |
| 5日目 | ◆ケーススタディ⇒評価結果報告書の作成(グループ作業) |
| 6日目 | ◆ケーススタディ⇒評価結果報告会と演習全体の振返り(グループ作業) ◆修了試験 |
注)遅刻・欠席は認められません。また、2日目以降については、かなり多くの課題(宿題)が課せられますので、ご留意下さい。
2.評価者養成講習日程
| 期 | コース名 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 |
| 第1期 | Aコース | 8月29日(水) | 8月30日(木) | 9月 4日(火) | 9月11日(火) | 9月18日(火) | 9月25日(火) |
| Bコース | 9月 5日(水) | 9月12日(水) | 9月19日(水) | 9月26日(水) | |||
| Cコース | 9月 6日(木) | 9月13日(木) | 9月20日(木) | 9月27日(木) | |||
| Dコース | 9月 7日(金) | 9月14日(金) | 9月21日(金) | 9月28日(金) | |||
| 第2期 | Eコース | 10月10日(水) | 10月11日(木) | 10月17日(水) | 10月24日(水) | 10月31日(水) | 11月 7日(水) |
| Fコース | 10月18日(木) | 10月25日(木) | 11月 1日(木) | 11月 8日(木) | |||
| Gコース | 10月19日(金) | 10月26日(金) | 11月 2日(金) | 11月 9日(金) |
3.講習会場
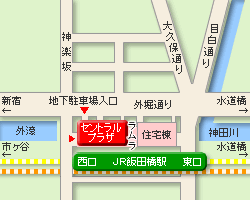 新宿区神楽河岸1−1セントラルプラザ(飯田橋駅前)
新宿区神楽河岸1−1セントラルプラザ(飯田橋駅前)
財団法人 東京都高齢者研究・福祉振興財団
13階研修室または15階多目的室
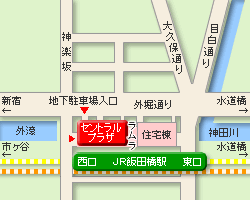 新宿区神楽河岸1−1セントラルプラザ(飯田橋駅前)
新宿区神楽河岸1−1セントラルプラザ(飯田橋駅前)財団法人 東京都高齢者研究・福祉振興財団
13階研修室または15階多目的室
4.募集定員
19年度の募集においては、下記のコースを募集します。
①「第1期(A〜Dコース)」の受講希望者(120名)(認証済評価機関のみ)
②「第2期(E〜Gコース)」の受講希望者(100名)(新規申請法人及び認証済評価機関)
(内訳 認証済評価機関:55名、新規申請法人: 45名(3名×15法人))
19年度の募集においては、下記のコースを募集します。
①「第1期(A〜Dコース)」の受講希望者(120名)(認証済評価機関のみ)
②「第2期(E〜Gコース)」の受講希望者(100名)(新規申請法人及び認証済評価機関)
(内訳 認証済評価機関:55名、新規申請法人: 45名(3名×15法人))
| コース 名 | ||
| 期 | コース | 定員 |
| 1 | Aコース | 30名 |
| Bコース | 30名 | |
| Cコース | 30名 | |
| Dコース | 30名 | |
| 2 | Eコース | 34名 |
| Fコース | 33名 | |
| Gコース | 33名 | |
Ⅱ 申込方法等
1.申込書類
(1)「評価者養成講習申込書」(受講者本人記入)
①「第1期」用申込書・・・・・A〜Dコース申込用
②「第2期」用申込書・・・・・E〜Gコース申込用
(2)「実務経験(資格要件)証明書」(受講者本人記入、内容を評価機関で確認)
●要件によっては、下記の必要書類(実績表、成果物等)を添付
①様式a・・・要件1 例示番号5−①、②、③・6−①、②
②様式b・・・要件1 例示番号7−①、②
③様式c・・・要件3 例示番号1
④様式d・・・要件3 例示番号2、3
(3)受講申込レポート(受講者本人がパソコン等にて作成することが必須)
(4)「評価者養成講習受講生推薦書」(評価機関記入)
●推薦書には様式が2種類あります。該当の推薦書をご記入ください。
①様式A・・認証済評価機関用
②様式B・・新規申請法人用
(1)「評価者養成講習申込書」(受講者本人記入)
①「第1期」用申込書・・・・・A〜Dコース申込用
②「第2期」用申込書・・・・・E〜Gコース申込用
(2)「実務経験(資格要件)証明書」(受講者本人記入、内容を評価機関で確認)
●要件によっては、下記の必要書類(実績表、成果物等)を添付
①様式a・・・要件1 例示番号5−①、②、③・6−①、②
②様式b・・・要件1 例示番号7−①、②
③様式c・・・要件3 例示番号1
④様式d・・・要件3 例示番号2、3
(3)受講申込レポート(受講者本人がパソコン等にて作成することが必須)
(4)「評価者養成講習受講生推薦書」(評価機関記入)
●推薦書には様式が2種類あります。該当の推薦書をご記入ください。
①様式A・・認証済評価機関用
②様式B・・新規申請法人用
2.申込方法
認証済評価機関及び新規申請法人は、上記(1)(2)(3)(受講者本人記入書類)とその他必要書類を取りまとめ、上記(4)推薦書を添えて、お申し込みください。(新規申請法人は認証申請と併せてお申し込みください。)
認証済評価機関及び新規申請法人は、上記(1)(2)(3)(受講者本人記入書類)とその他必要書類を取りまとめ、上記(4)推薦書を添えて、お申し込みください。(新規申請法人は認証申請と併せてお申し込みください。)
※申込書等は、持込時間内に事務局に来所のうえ、提出して下さい。
その場で、申込み書類の記入漏れ等の確認作業を行います。
その場で、申込み書類の記入漏れ等の確認作業を行います。
3.申込上の注意
(1)認証済評価機関について
・1名から申し込むことができます。
・第1期及び第2期にお申込いただくことができます。(ただし、第2期については、新規申請法人も含まれることをご考慮いただいたうえ、お申込ください。)
・同一人物が、1期と2期の両方に申し込むことはできません。どちらかの期を選んでお申込みください。
・申込多数の場合、認証済評価機関の中で、応募評価機関数及び評価実績等を勘案し、申込人数の調整をする場合があります。
(2)新規申請法人について
・1法人につき、少なくとも3名一組から、多くとも5名一組でお申込みください。ただし、4名の場合は1名が補欠、5名の場合は2名が補欠となります。
・5名一組(補欠2名含む)で申し込まれ、資格審査において、どなたかが資格要件を満たしていなかった場合、補欠の方が繰り上がります。但し、優先順位の上位3名の方が、資格審査における資格要件を満たしている場合は、補欠の方は受講することができません。
・3名一組で申し込まれた場合、1名でも資格要件を満たしていなければ、その新規申請法人は法人として申請の要件を欠くことになりますのでご注意下さい。
・第2期にお申込下さい。(新規申請法人については、第1期のお申込は受付けられませんのでご注意下さい。)
・申込を行う上位の3名は、必ず福祉分野並びに経営分野の資格を有する方の組合せでお申込下さい。
・新規申請法人が予定の15法人を超えた場合は、最初に、新規申請法人の中で、法人単位の抽選を行います。
(1)認証済評価機関について
・1名から申し込むことができます。
・第1期及び第2期にお申込いただくことができます。(ただし、第2期については、新規申請法人も含まれることをご考慮いただいたうえ、お申込ください。)
・同一人物が、1期と2期の両方に申し込むことはできません。どちらかの期を選んでお申込みください。
・申込多数の場合、認証済評価機関の中で、応募評価機関数及び評価実績等を勘案し、申込人数の調整をする場合があります。
(2)新規申請法人について
・1法人につき、少なくとも3名一組から、多くとも5名一組でお申込みください。ただし、4名の場合は1名が補欠、5名の場合は2名が補欠となります。
・5名一組(補欠2名含む)で申し込まれ、資格審査において、どなたかが資格要件を満たしていなかった場合、補欠の方が繰り上がります。但し、優先順位の上位3名の方が、資格審査における資格要件を満たしている場合は、補欠の方は受講することができません。
・3名一組で申し込まれた場合、1名でも資格要件を満たしていなければ、その新規申請法人は法人として申請の要件を欠くことになりますのでご注意下さい。
・第2期にお申込下さい。(新規申請法人については、第1期のお申込は受付けられませんのでご注意下さい。)
・申込を行う上位の3名は、必ず福祉分野並びに経営分野の資格を有する方の組合せでお申込下さい。
・新規申請法人が予定の15法人を超えた場合は、最初に、新規申請法人の中で、法人単位の抽選を行います。
4.申込受付期間
持込期間 平成19年5月7日(月)〜6月8日(金)(来所持参のみ、郵送不可)
持込時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00
持込期間 平成19年5月7日(月)〜6月8日(金)(来所持参のみ、郵送不可)
持込時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00
5.申込先
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1−1 飯田橋セントラルプラザ13階
財団法人 東京都高齢者研究・福祉振興財団内
東京都福祉サービス評価推進機構 事業部 評価支援室 研修担当 北堀(きたぼり)・小池(こいけ)・中田(なかた)
電話 03-5206-8750 FAX 03-3235-8533
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1−1 飯田橋セントラルプラザ13階
財団法人 東京都高齢者研究・福祉振興財団内
東京都福祉サービス評価推進機構 事業部 評価支援室 研修担当 北堀(きたぼり)・小池(こいけ)・中田(なかた)
電話 03-5206-8750 FAX 03-3235-8533
Ⅲ 受講者の決定
(1)受講資格要件及びレポートについて申込書類により審査し、受講者を決定します。
なお、書類審査通過者が定員を上回っている場合には、下記により決定します。
①認証済評価機関の場合
・まず、応募した1評価機関あたり、貴機関における要件整備等(認証要綱第2条第9号規定「福祉・経営分野各1名以上配置」)を考慮の上、1名を割り振ります。
・次に、評価実績等を勘案し、抽選などの方法により決定します。
②新規申請法人の場合
・応募した新規申請法人の中で、法人単位の抽選を行い決定します。
・提出された書類についてはお返ししませんので、ご了承下さい。
(2)受講決定後、受講者決定通知を評価機関・申請法人宛に発送いたします。
第1期及び第2期受講生・・・・・7月中旬発送予定
受講コースについてもあわせて、ご連絡いたします。
(1)受講資格要件及びレポートについて申込書類により審査し、受講者を決定します。
なお、書類審査通過者が定員を上回っている場合には、下記により決定します。
①認証済評価機関の場合
・まず、応募した1評価機関あたり、貴機関における要件整備等(認証要綱第2条第9号規定「福祉・経営分野各1名以上配置」)を考慮の上、1名を割り振ります。
・次に、評価実績等を勘案し、抽選などの方法により決定します。
②新規申請法人の場合
・応募した新規申請法人の中で、法人単位の抽選を行い決定します。
・提出された書類についてはお返ししませんので、ご了承下さい。
(2)受講決定後、受講者決定通知を評価機関・申請法人宛に発送いたします。
第1期及び第2期受講生・・・・・7月中旬発送予定
受講コースについてもあわせて、ご連絡いたします。
Ⅳ 受講料等 ¥29,000
受講料として¥29,000が受講者の負担となります。当財団専用の「コンビニエンスストア払込票」をご利用いただき、振込みをしていただきます。(振込方法については、受講決定通知送付の際お知らせします。)
受講料として¥29,000が受講者の負担となります。当財団専用の「コンビニエンスストア払込票」をご利用いただき、振込みをしていただきます。(振込方法については、受講決定通知送付の際お知らせします。)
Ⅴ 受講資格要件
受講者の推薦にあたっては、講習受講申込者が、当機構が定める下記の受講要件を満たしていることを確認してください。
資格要件については、別紙1「評価者養成講習応募要件の具体的例示」をご参照いただき、要件1〜4の例示に該当するか、ご確認ください。
また、要件1〜4にあてはまらないが、それに相当すると判断される受講者を推薦する場合は、その判断理由を提示の上、要件5としてお申し込みください。
なお、要件5としてお申し込みの場合、審査の結果、要件5として認められなかった場合は、受講ができませんので、ご了承の上、お申し込みください。
受講者の推薦にあたっては、講習受講申込者が、当機構が定める下記の受講要件を満たしていることを確認してください。
| 資格要件 |
| 次の要件のうち1つ以上あてはまること 要件1 福祉・医療・保健業務を3年以上経験している者 要件2 組織運営管理等業務を3年以上経験している者 要件3 調査関係機関等で調査業務や経営相談を3年以上経験している者 要件4 福祉・医療・保健・経営分野の学識経験者で当該業務を3年以上経験している者 要件5 その他、上記と同等の能力を有していると機構が認める者 |
資格要件については、別紙1「評価者養成講習応募要件の具体的例示」をご参照いただき、要件1〜4の例示に該当するか、ご確認ください。
また、要件1〜4にあてはまらないが、それに相当すると判断される受講者を推薦する場合は、その判断理由を提示の上、要件5としてお申し込みください。
なお、要件5としてお申し込みの場合、審査の結果、要件5として認められなかった場合は、受講ができませんので、ご了承の上、お申し込みください。
Ⅵ 修了認定について
修了認定された受講者には、修了証を発行します。
●修了認定には
(1)講習最終日に、修了試験を実施します。講習全日程出席のほか、修了試験に合格する必要があります。
(2)修了認定のためには、修了試験に合格し、かつ評価実習およびそのレポート等の提出が必須となっています。(評価実習については次項参照)
修了認定された受講者には、修了証を発行します。
●修了認定には
(1)講習最終日に、修了試験を実施します。講習全日程出席のほか、修了試験に合格する必要があります。
(2)修了認定のためには、修了試験に合格し、かつ評価実習およびそのレポート等の提出が必須となっています。(評価実習については次項参照)
Ⅶ 名簿登載について
評価者として活動するには、評価者名簿への登載が必要です。修了証発行後、30日以内に名簿登載を行なわなければ修了証の効力は無効となります。
評価者として活動するには、評価者名簿への登載が必要です。修了証発行後、30日以内に名簿登載を行なわなければ修了証の効力は無効となります。
評価実習について
①認証済評価機関の場合
評価機関が平成19年5月7日以降に実施する評価に補助者として参加し、現地調査に同行し、その経験について報告書を作成し機構に提出してください。
評価実習は、講習の前や講習の期間中に行ってもよいこととします。
機構では、実習先の調整はいたしませんのでご注意下さい。
②新規申請法人の場合
下記のいずれかの方法により実施して下さい。豩の場合のみ、機構で実習先を調整いたします。実習の調整は、6日間の講習後に行います。
豗 認証済評価機関が、平成19年5月7日以降に実施する評価に補助者として参加し、現地調査に同行し、その経験について報告書を作成し機構に提出して下さい。
豩 評価実習に協力してくれる福祉施設において、福祉の現場を体験し、その結果報告書を機構に報告して下さい。(変更の場合があります)
※評価実習報告書は、修了試験の合格通知が届いてから2ヶ月以内に提出していただきます。①認証済評価機関の場合
評価機関が平成19年5月7日以降に実施する評価に補助者として参加し、現地調査に同行し、その経験について報告書を作成し機構に提出してください。
評価実習は、講習の前や講習の期間中に行ってもよいこととします。
機構では、実習先の調整はいたしませんのでご注意下さい。
②新規申請法人の場合
下記のいずれかの方法により実施して下さい。豩の場合のみ、機構で実習先を調整いたします。実習の調整は、6日間の講習後に行います。
豗 認証済評価機関が、平成19年5月7日以降に実施する評価に補助者として参加し、現地調査に同行し、その経験について報告書を作成し機構に提出して下さい。
豩 評価実習に協力してくれる福祉施設において、福祉の現場を体験し、その結果報告書を機構に報告して下さい。(変更の場合があります)
(2ヶ月以内に提出することが不可能な場合、速やかに機構までご連絡をお願いいたします。)
Ⅷ その他
・新規申請法人からのお申込みの場合は、必ず認証申請書類と併せてお申し込み下さい。
・お申込いただいた個人の情報については、評価者養成講習及び評価者名簿登載時以外は、使用いたしません。
・新規申請法人からのお申込みの場合は、必ず認証申請書類と併せてお申し込み下さい。
・お申込いただいた個人の情報については、評価者養成講習及び評価者名簿登載時以外は、使用いたしません。
Ⅸ 問い合わせ先
東京都福祉サービス評価推進機構
財団法人 東京都高齢者研究・福祉振興財団
事業部 評価支援室 研修担当 北堀(きたぼり)・小池(こいけ)・中田(なかた)
TEL03−5206−8750 FAX03−3235−8533
e-mail hyoka@fukushizaidan.jp
東京都福祉サービス評価推進機構
財団法人 東京都高齢者研究・福祉振興財団
事業部 評価支援室 研修担当 北堀(きたぼり)・小池(こいけ)・中田(なかた)
TEL03−5206−8750 FAX03−3235−8533
e-mail hyoka@fukushizaidan.jp
●認証評価機関用(自己解凍形式ファイル)
●新規申請法人用(自己解凍形式ファイル)